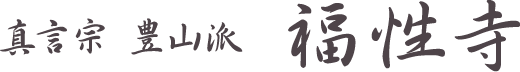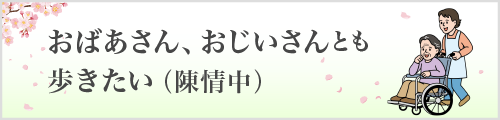旦那様が亡くなられた後、50年以上や60年以上も「独身」であった仏様の年回忌法要(一周忌や三回忌など)を、この2週間に2回続けて執行しました。もちろん、独身をご自分で選択したわけではありません。旦那様が早く亡くなり、お子様をお育てになり80歳以上や90歳以上で亡くなりました。旦那様が亡くなった直後に福性寺のお檀家になりました。当時の福性寺をご覧下さい(写真)。かなり、ボロボロで貧しそうす。
お子様方を立派にご養育しました。生前を思い出しますと、大変温厚な方ばかりです。また、墓参には、とても頻繁においでになりました。その上、施餓鬼会や読経会にも欠かさずご出席を頂きました。住職は本当に有難かったですね。
生前にもう少し、お話をお聞きしたかったです。お子様方からお話をお聞きしますと、ご家庭の中では、お静かで温厚であったとのことです。上手に表現できませんが、風格がありました。
一方、通夜や葬儀・告別式では、福性寺住職作の諷誦文(ふじゅもん・ふうじゅもん、仏教的な追悼文)を読みます。その諷誦文の中では、故人の長い間の独身についても記述し、故人の人生を称賛しました。
ご自宅の近くの寺のお檀家になり、墓参や行事に参加し、住職の話をお聞き頂き、少しだけでも人生や生きがい、心の平安にプラスになったことがありましたら、有難いのですが。最近、流行のスピリチュアルケアとは何か?を考えることがあります。

昭和34年(1959年)撮影の旧本堂 ブロック塀の新設時です 山門の左に六地蔵様 (六地蔵塔)右に3本の杉の木と今もある銀杏の木が見えます この本堂は関東大震災後大正13年(1924 年)頃に落慶しました(「福性寺の歴史第6版」より)仮本堂です