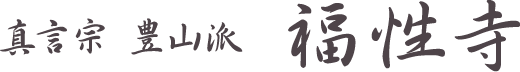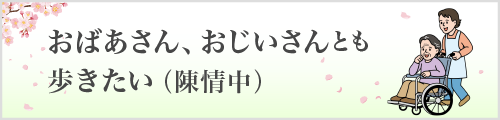「梶原の渡し(明治42年1909年~昭和36年1961年)」について書いてきました。
「合名渡船場」の世話人(法人役員)の8人が、渡しの運営を全て決めていました。最初の船頭は阿出川五三郎氏(昭和11年1936年亡)でした。五三郎氏に関しては、すこし疑問があります。詳しく知りません。今後、確かめたいと思います。
最初の船頭さんに関する情報をお持ちの皆様はご教示ください。荒川放水路開削時に自宅を南宮城に移転したとの記録があります(註 足立史談)。
その後の船頭さんは、ご子息(写真、昭和62年1987年89歳亡)でした。岸近くの浅瀬では、長い竹竿を使い、沖では櫓を使っていました。宮城側では竿を使うことが多かったと思います。
私の知っている頃の船頭さんは、瘦身で日焼けをしていました。
渡船の船縁(ふなべり、漕艇用ボートのガンネル)は、帯状に幅広くなっていて、浅瀬では竿を使いながら船縁の上を歩いて船を押していました。力仕事です。とても身が軽かったです。
夏場では、幅の狭い船縁の上を素足の雪駄ばきで歩く姿を見て「すごいな!素人ではない」と思って乗っていました。船縁は狭いので、雪駄がはみ出していました。船頭さんを信頼していましたので、「安全な乗り物」と思っていました。
冬の履物は覚えていません。しかし「梶原の渡し(3)梶原渡しの開設」の記事の写真では、足袋に雪駄をはいています。
川の流れは、引き潮や上げ潮により川の流れの方向が変わります。上流に向かったり、下流に向かったりで、円弧のように操船していました。また、風の方向も考慮していました。
乗っている身としては、船の舳先(へさき、船首)があらぬ方向を向いているので、本当に無事に対岸に到着するか気になることがありました。しかし、計算されていたように、ぴったりと対岸の発着場につきました。
私の記憶では、渡船は大きな船(写真)と小さな船の2艘があったと思います。
梶原の渡しに関する情報をください。
(註)絹田幸江.荒川放水路物語(4)足立史談 第167号(4)昭和57年1月20日印刷発行 編集発行足立区教育委員会
いろいろな人に乗船の記憶があります。
令和3年2021年8月4日蓮のモデル料? トマトのお供えhttps://fukushoji-horifune.net/blog/archives/9639