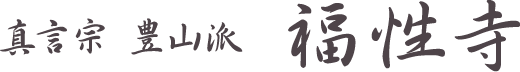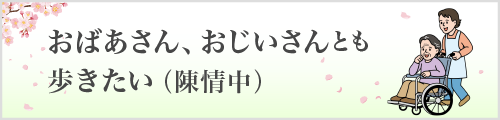渡船営業を始めたころ(明治42年1909年)の渡船賃は、大人片道1銭でした。2024年の物価との比較では、15円(日銀統計基準)~200円(食物価格基準)でしょうか。子供は半額。荷積車・人力車・自転車片道1銭5厘、荷積馬車・牛馬片道2銭5厘でした。営業時間は午前6時から午後8時まででした(註1 註2)。

宮城に遊びに行く子供 宮城側は隅田川のカーブの内側で浅瀬が続いていました 船頭さんは笠 雪駄と黒腹掛けです 子供は麦わら帽子と足もとに虫かご たま網 第1次防潮堤完成工事開始昭和24年1949年から昭和31年1956年完成(註3)前の宮城の岸が見えます 渡船の船縁が修理されています 写真提供 阿出川光子氏
下野紡績への通勤客には割引をした定期券を発行していました(註2)。
会社組織ですが、利益は上がったのでしょうか。このあたりは、どなたにお聞きすればよいのでしょうか?
その後、渡船賃は上昇し、昭和初期に2銭、昭和17年ごろ5銭、昭和36年ごろは大人が10円となりました(註1)。現在の25~50円(企業・消費者物価指数)でしょうか。
ちなみに、私が小学生のころの都電料金は13円、往復切符(なつかしい!)は25円でした(昭和36年ごろまで)。
私が乗った頃の渡しの金額は、記憶がありません。多分、父が払っていたからと思います。
私が宮城の沼地などに遊びに出かけた頃は、通勤者は少なくなり日中でもあることから貸し切り状態であることがありました。
子供だけで宮城に出かけたことがあります。宮城の沼と池や小川での遊び(掻い掘り、かいぼり)や釣りは、堀船の子供のちょっとした冒険の場所となっていました。
父と藪の中のクコの実(漢方薬となります)とりは、楽しい思い出です。
註1 足立風土記稿地区編3: 39ページ. 編集足立区郷土博物館足立教育委員会平成12年3月発行
註2 高梨輝憲「わが町の昔を語る」167-168. 昭和48年1973年4月184ページ
註3 望月崇、島正之、篠田裕.隅田川における防潮堤建設史(自由投稿論文)土木史研究第18号平成10年1998年5月(表2)