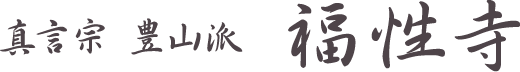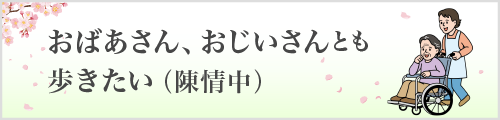梶原の渡しについて、記事を書いてきました。「写真がいい」とお檀家から聞きました。ありがとうございます。文章はどうでもいい?なくてもいい!とからんだり(笑)しませんでした。(笑)=ジョークの意味です。
下野紡績工場に通勤のために梶原の渡しは開設されたと書きました。具体的な毎日の乗船者数など、営業の実態の記録の所在を知りません。
「梶原渡船場跡」の説明板(註1)によると、荷車の運賃があるように、駒込にあった野菜市場(駒込のやっちゃば)に野菜を出すための交通路としても利用され、毎日15台以上が隅田川を船で往復したそうです。第2次世界大戦中には、足立区方面などに軍需工場が多くなり、工場へ通う通勤者の行き帰りの足としても混雑したそうです。これは阿出川幸平氏かそのご子息からの聞き取りと思います。
野菜の季節には、駒込市場への出荷の車を毎日15台以上、五色桜の時季には近隣のレンガ工場の伝馬船2艘も応援しました(註2)。
駒込市場は、江戸時代から神田・千住と並ぶ江戸の三大野菜市場でした。昭和12年に巣鴨(豊島青果市場)に移転しました。
本郷通りを通ると、文京区本駒込の天栄寺の前に「史跡文化財駒込土物店跡」の御影石の石碑を見ることができます。車窓からも見えます。このあたりに「駒込やっちゃば」があったらしいです。
私(昭和24年生)は、物価の安い梶原銀座商店街への買い物客を乗せていたとも聞きました。同様の記事があります(註3)。
註1 梶原渡船場跡説明板 東京都北区教育委員会 平成8年1996年3月
註2 足立風土記稿。足立風土記稿地区編3江北(編集足立区郷土博物館 平成12年3月発行 足立教育委員会)
註3 北区地域振興部観光振興担当. 東京都北区観光ぺージhttp://www.kanko.city.kita.tokyo.jp/spot/360-2/