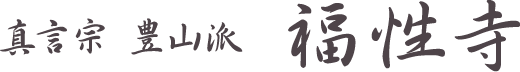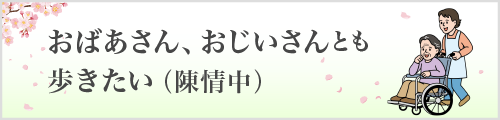梶原の渡し(合名渡船場)は、昭和29年1952年に会社組織としては、解散しました。その後は個人営業となりました。最後の船頭さんは阿出川平七氏です。
それでも、昭和36年1961年に、その姿を消しました。北区では最後の隅田川を横断する渡し場でした(註1)。
私の記憶でも、昭和37年1957年にキリンビール東京工場ができるまでは、東洋紡績王子工場の跡地には、人の出入りはほとんどありませんでした。
昭和24年1949年から国により第一次高潮対策事業が実施され、防潮堤108kmと水門38ヵ所を整備して、昭和31年1956年にほぼ完成しました。このため、堤防天端が地面より1mの高さとなっていました。堀船側では水面近くの発着場まで降りるために、木製の急坂をおりていました。
私が梶原の渡しを利用したころは、堤防が完成した後でした。あまりに急で、渡船場(発着場)まで降りることが、こわかったです。人と自転車以外は、発着場まで降りることはできなかったと思います。発着場も当初の2×6間よりも、よほど狭かったと思います。
宮城側の堤防工事は遅れていたと記憶しています。
昭和30年1955年ごろ、対岸(宮城)で釣りや遊びのために、父と一緒に何度か渡し船で出かけました。渡し船で自転車を運ぶ姿は見ました。しかし、野菜や牛馬を運ぶ姿を見たことがありません。トラックの時代となっていたからであると思います。
対岸の宮城で休息をする阿出川平七さんに手を振ると、空の渡し船で迎えに来てもらうことができ、堀船から宮城まで運んでくれました。
船頭の阿出川平七さんは63歳ごろまで船頭さんをしていたのでしょう。
渡し船に積み残しの人がでるほど繁盛していることは、なかったと思います。最後のほうは、渡し船が運行されていない日があり、がっかりしたことがあります。
この後の記事では、現在の渡船場跡の写真や豊島橋と小台橋の航空写真をアップします。
(註1) 高梨輝憲「わが町の昔を語る」昭和48年1973年4月184ページ
さて、今日は土曜日です。土曜日と日曜日はお檀家の年回忌法要を執式しています。お寺に関することや健康などにご相談のある皆様は、2時ごろからご来寺下さい。