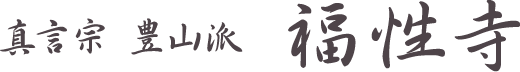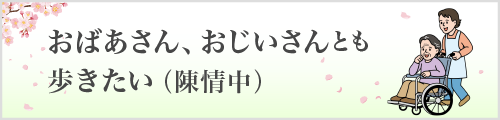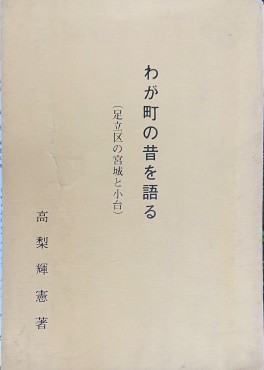明治42年1909年に「梶原の渡し」が開設されました。この点に関しては高梨輝憲氏(故人)著「わが町の昔を語る(足立区の宮城と小台)」(註1)に詳しく書かれています。
東京府知事阿部浩氏あての「渡船営業願」(明治42年1909年5月)があります。この中には、下野紡績の工場の建設工事のために、数百人が、また完成後は、なお千人が通うことになるためと、その交通の不便の解決のために「渡船営業願」が出されたとあります。
王子町大字堀之内側(現在の堀船1~3丁目、右岸)から、渡船業願人 石井惣吉氏(福性寺檀徒昭和10年1935年亡)、江北村大字宮城側から下川金太郎氏と阿出川伊三郎氏が保証人になっています。下川金太郎氏についての詳細は不明です(郷土史家 下川信明氏令和7年2月6日談)。阿出川伊三郎氏は、大正元年には江北村助役、大正2年6月から2年10カ月間、江北村長を務めました(「南足立郡誌」東京府南足立郡役所大正5年7月28日発行)
石井惣吉氏は、右岸の地主でした。保証人の2人は左岸の宮城に住み、同様に地域の有力者で地主でした。
「合名渡船場」資金帳によると、世話人(法人役員)は下川姓5人(金太郎、春吉、治輔、晴太郎、金七氏)、阿出川姓2人(伊三郎、徳松氏)と清水亀次郎氏の計8人でした。その他、多数が株金の出資者で会社組織でした。世話人の全ては、左岸、宮城側の住人でした。つまり、名前は「梶原の渡し」ですが、事業の実態は宮城にありました。当初の集金総株金は200円でした。
こちらは別の話題ですが、世話人の多くの皆さんが荒川放水路の敷地に住んでいたために移転しています。江北村宮城では、70戸中49戸が大正時代の初めに移転しました。
支出についても記述があります。新造船代90円、新規渡船場40円30銭、道路新設工事13円でした。渡船場(発着場)の規模は、宮城側、堀船側がともに6×2間の広さでした(註2)。株金を募集して、船と施設をつくって営業を開始しました。

宮城側の渡船場(発着所) 当初のものよりかなり広いことがわかります 船頭の阿出川平七氏が凛々しいです 堀船福性寺側の岸が見えます 昭和24年に工事が始まり昭和31に完成した第1次防潮堤が対岸見えます 右上の白い四つの点は漕艇用ボート 右上の煙突は東洋紡績王子工場であった東京陸軍第1造兵廠跡(大蔵省管理)と思われます 浅瀬では長い竹竿で操船をしていました(阿出川光子氏提供)
渡しの名前は対岸の堀之内の古名「梶原堀之内村」からとったと書かれています。世話人の全てが宮城村に住み、主に宮城村の事業であったにもかかわらず、対岸の名前を採用するとは、奥ゆかしさを感じます。
これは、編集協力者で郷土史家の下川信明氏によれば、 足立区宮城の住人の目は、交通機関などの問題で、対岸の堀船に向いていたためではないかとのことでした(令和7年2025年2月6日談於福性寺)。
この時代やこの後も、対岸の江北村の皆さんは、小台の渡し、梶原の渡しや豊島の渡しで隅田川をわたって、王子駅、田端駅、尾久駅、上中里駅や王電(現在の都電)を利用した皆さんがいたようです。このホームページの「梶原の渡し(2)時代の背景」に書きました。
(1) 高梨輝憲「わが町の昔を語る」昭和48年1973年4月 「梶原の渡し」については183~189ページ(自費出版)
(2)足立風土記稿。足立風土記稿地区編3江北(編集足立区郷土博物館 平成12年3月発行 足立教育委員会)
令和7年2025年2月12日梶原の渡し(2)時代の背景https://fukushoji-horifune.net/blog/archives/27045
令和7年2025年2月9日梶原の渡し(1)https://fukushoji-horifune.net/blog/archives/26985
令和6年2024年8月9日「堀船郷土史」漕艇競技のメッカ「堀船・尾久」隅田川漕艇https://fukushoji-horifune.net/blog/archives/24147